 STAFF INTERVIEW
人を知る スタッフ座談会
STAFF INTERVIEW
人を知る スタッフ座談会
STAFF INTERVIEW
人を知る スタッフ座談会

「屋外に看板をつけられない」という制約をチャンスに変え、内照式看板とデジタル時計を組み込んだ挑戦的な案件に、営業・デザイン・製作・工務が一丸となって取り組みました。
未経験の技術も各部署の専門知識とチームワークで乗り越え、街の景観を彩る達成感を共有。現場スタッフによる生の声と仕事への情熱を、座談会形式でお届けします。


制作課 デザイナー
2023年入社
長澤 佑佳
長澤 佑佳

制作課 制作担当
2023年入社
片小田 優衣
片小田 優衣

工務課 課長
2012年入社
仁賀奈 勇軌
仁賀奈 勇軌

営業3課 課長
2019年入社
水溜 利彦
水溜 利彦

営業1課 課長
2008年入社
小嶋 祥一
小嶋 祥一
プロジェクトデータ
| お客様 | 有限会社 楽天地様(元祖もつ鍋もつ焼き楽天地 薬院渡辺通り店) |
|---|---|
| 設置場所 | 電気ビル 共創館(福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号2階) |
| 特徴 | 幅約27メートル×高さ2.5メートルの大型看板、デジタル時計付き |

今回の大型案件の受注経緯を教えてください。
水溜:
楽天地さんとの繋がりは、代表の水谷社長と弊社代表の渕上が地域企業交流会で知り合ったことがきっかけです。6年前に博多駅前で大型看板を手がけ、3年前にも天神で大型看板を製作しました。今回も立地の良さから、これまで楽天地さんのブランドや歴史を知る業者に任せたいという水谷社長のご意向で発注をいただきました。
小嶋:
そうですね、特に今回の設置場所「電気ビル」は福岡では条件も厳しく設けられている場所です。弊社のこれまでの看板デザインの品質と施工の安全性、施工の正確性の実績を評価していただいています。
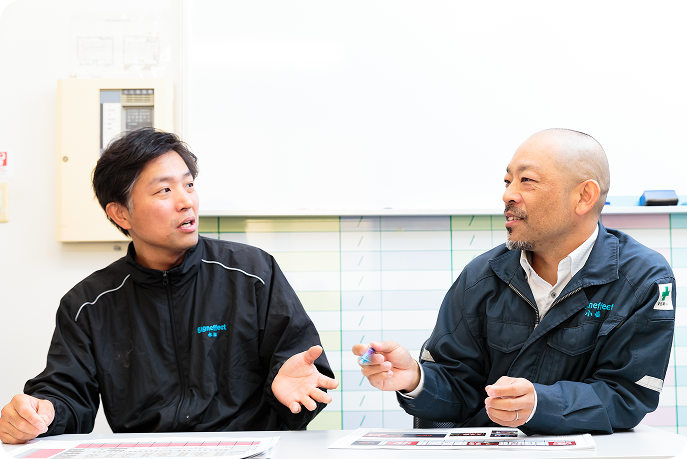
サインエフェクトさんのこれまでの多種多様な実績と、技術面はもちろん、会社の財務体質なども含め「ここに任せておいたら大丈夫」という信頼があってこその受注だったわけですね。
水溜:
はい、そのとおりです。信頼関係があってこその受注だと思います。
技術的チャレンジ – 制約を強みに変える発想
今回の案件ではどのような技術的な課題がありましたか?
水溜:
今回の設置場所は、渡辺通り1丁目という交通量の多い大きな交差点に面したガラス張りのビルです。お客様からは「全てを使って目立つ看板を作りたい」というご要望をいただきました。しかし、この電気ビルには「屋外に看板をつけられない」という条件がありました。
幸いなことに全面ガラス張りのビルだったので、中から外に向けて看板をつける方法を考え、全面を活用するコンセプトで始まりました。
幸いなことに全面ガラス張りのビルだったので、中から外に向けて看板をつける方法を考え、全面を活用するコンセプトで始まりました。

条件のデメリットをプラスに持っていく、逆転の発想が今回のコンセプトにつながったということですね。
水溜:
そうですね。お客様のご要望と建物の制約という課題をチャンスに変えられたのは、当社の強みだと思います。
具体的に、どのような苦労がありましたか?

水溜:
全面が一遍通りでできるものではなく、窓が1m80センチ間隔で間仕切りがあるんです。それぞれの区画に小さな看板を並べていく必要がありました。さらに、建物内部は看板を取り付けるために壁に穴を開けたりすることも禁止されていました。
長澤:
デザイン面でも、横長の一体感のあるデザインができず、区切りがある中で配分を考える必要がありました。区切りの線が入ることでデザインが途切れてしまうところが課題でした。
片小田:
内照式の目立つ看板を作りたいということで、中から光るサイン(内照サイン)を検討しましたが、設置に対して建物を傷つけないという条件に加え、重量問題や電気容量の問題も課題としてありました。
デジタル時計 – シンボルとしての機能性
デジタル時計のアイデアはお客様からだったのですか?
水溜:
はい。楽天地の水谷社長から「時計をつけたい。みんな絶対見るから。シンボルになると思うから」という要望をいただきました。実際、交差点に面した立地なので、歩行者や車からも見える時計は非常に効果的なアイデアでした。水谷社長は以前の店舗でも独自のアイデアで集客に成功されています。時計は単なる時間を知らせるだけでなく、店舗のシンボルとして「あの時計がある店」と記憶してもらえる効果もあります。また、時計を見るために足を止める人も多いので、その間に店舗全体の看板も目に入るという相乗効果も期待できます。
仁賀奈:
工務の立場から見ても、時計は施工上の挑戦でもありましたね。特に今回のような大型看板に組み込む形での設置は、重量バランスや取り付け強度の計算が複雑でした。夜間工事という制約の中で、安全に確実に取り付けるために、事前のシミュレーションを何度も行いました。大規模な看板工事では、こうした綿密な準備が成功の鍵になります。

時計のメンテナンスのしやすさについてはどのような工夫をされましたか?

片小田:
裏から抜けるような構造にしています。店舗スタッフが安全にアクセスできる位置に設計し、メンテナンス性を考慮した形にしています。表示面は分割でできていて、どこか消えてしまうとそこの部分ごと取り替える必要があるので、正面からの取り外しがしやすく、また取り付けやすい構造に工夫しています
仁賀奈:
施工面でも、将来のメンテナンスを考慮した取り付け方法を採用しました。通常の看板工事では壁面に直接固定するケースが多いのですが、今回は建物を傷つけない条件があったため、専用の自立型フレームを設計し、そこに時計ユニットを組み込む方法を考案しました。これにより、後日部品交換が必要になった場合でも、看板全体を取り外すことなく作業ができます。こうした現場での工夫が我々工務の腕の見せどころですね。
これまでも同様のデジタル時計の製作経験はありましたか?
片小田:
いいえ。今回が初めての挑戦でした。ですが、当社ではこうした未経験の案件でも前向きに取り組む文化があります。まず徹底的に調査研究を行い、電子部品メーカーや専門家への相談も重ねました。複数の設計案を作成して検証し、最終的には耐久性と視認性、そしてメンテナンス性を両立させる設計にたどり着きました。こうした新しい挑戦が私たちの技術力向上につながっていると思います。
チーム連携 – 専門性を活かした協働
設計、製作、施工の連携について教えてください。
このような難しい案件をチームでどう乗り越えましたか?
水溜:
基本的には営業が構想を考え、図面を共有することがポイントです。今回はデジタルサイネージと内照看板の電源が重要でした。構造上の制約を考慮して「ここに柱があるので、こっちから電源を出さなければならない」など、図面を見ながら一緒に作り上げていきました。
仁賀奈:
デジタルサイネージは看板業界でも特化した業者が行うことが多く、通常の看板と組み合わせるのは特殊です。正直言うと、私たちも未経験でした。しかし、経験のないことでも、チームですり合わせながら進めていきました。この仕事は横の連携や情報共有がなければ、大きな事故やミスにつながりかねません。だからこそチームワークが重要です。製作側からすると、内照看板の取り付け方法は分かっても、経験したことのないデジタルサイネージの取り付け方法については「こうした方がいいのでは」「金物もこういう加工をした方がいい」など、相談しながら進めました。
水溜:
それぞれの分野で、取り付け方法や見せ方の問題などを議題として持ち上げ、考えていきました。
小嶋:
そうですね、その点は私たちの強みだと思います。それぞれの知識を活かし、理論上ではこういう取り付け方ができても、実際に作るとなるとどういう順番でつけるべきかなど、お互い「餅屋は餅屋」で話し合いました。


予想外の問題への対応力
チーム連携と課題解決について具体的なエピソードはありますか?
水溜:
今回は夜間工事という特殊な条件で、時間内に終わらせる必要がありました。
私も営業担当として現場に行き、スタッフや職人の不安解消に努めました。
営業はこうしたい、職人はこうした方がいいという意見を持ち寄って、その場で解決していきました。
私も営業担当として現場に行き、スタッフや職人の不安解消に努めました。
営業はこうしたい、職人はこうした方がいいという意見を持ち寄って、その場で解決していきました。
仁賀奈:
そういった現場での連携が当社の強みだと思います。
採用の視点で言うと、新しく入った方でも知識を活かし「こうした方がいいのでは」という意見を自由に言える環境があります。
自由に意見を採用して現場を組み立てていける会社体制です。
採用の視点で言うと、新しく入った方でも知識を活かし「こうした方がいいのでは」という意見を自由に言える環境があります。
自由に意見を採用して現場を組み立てていける会社体制です。
小嶋:
別の案件ですが、内照式の看板で外部のデザイナーから指定された材料が間違っていて、光らせた瞬間に想定していた色と違うものが出てしまったことがありました。
夜間工事の終わりの時間で全員フリーズする場面もありましたが、幸い店舗オープン前だったので、一旦そのままにして急ぎで資材を発注し直し、工期内に間に合わせることができました。
夜間工事の終わりの時間で全員フリーズする場面もありましたが、幸い店舗オープン前だったので、一旦そのままにして急ぎで資材を発注し直し、工期内に間に合わせることができました。
仁賀奈:
これは内部や現場の管理連携が取れていないとできないことです。工事が終わった後や途中で問題があっても、すぐに報告しない体制のところもありますが、当社はスタッフがしっかりサポートしながら、一人一人が責任を持ってお客様のために動いています。
技術力向上と人材育成 – 成長できる環境
技術職の方に伺います。入社後、どういう部分で成長を感じていますか?


仁賀奈:
工務として入社した当初は、基本的な取り付け作業しかできませんでしたが、先輩方の指導のもと、様々な現場を経験する中で技術が身についていきました。特に大型看板の施工では、安全管理から資材の搬入計画、工程管理まで一貫して任されるようになり、現場責任者としての判断力も養われました。何より、自分が施工した看板が街に残るという達成感は何物にも代えがたいですね。
片小田:
私は製作担当ですが、工務との連携が重要なので、常に現場の視点を意識するようになりました。上司からは一方的な指示ではなく、「こういうものを作る」と伝えられたときに、私がどう作るか、現場での取り付けやすさも考慮して意見を言う機会があります。それを認めてもらえる環境があるので、自分で考える力が身につきました。
長澤:
デザイン部門でも、実際の施工を考慮したデザインが重要です。最初は見た目だけを考えていましたが、工務の方々と話す中で、取り付け方法や耐久性なども考慮したデザインを提案できるようになりました。チーム全体で製品の質を高める意識が身についたと思います。
業界の可能性と働く意義
それぞれの立場から、これから一緒に働く方へメッセージをお願いします。
仁賀奈:
工務は営業が受けた仕事を製作が作り、最後に現場の人間が収める流れです。お客さんとの接点を最後に持ち、責任を持って完遂する必要があり、プレッシャーもありますが、収めた後の達成感は格別です。
自分が携わった看板が街に残っていくことを考えると、景観を作っている自信や楽しみがあります。
また、沖縄や北海道など全国各地に現場があるので、そういう楽しみ方も見つけてほしいと思います。
自分が携わった看板が街に残っていくことを考えると、景観を作っている自信や楽しみがあります。
また、沖縄や北海道など全国各地に現場があるので、そういう楽しみ方も見つけてほしいと思います。


片小田:
仕事の内容は幅広いので、確実に自分の得意は見つけられる会社です。
看板会社は手先が器用でないと入れないと思われがちですが、実際はいろんな人がいて、それぞれ自分ができることが見つけられます。
経験がなくても全く違う分野に触れる機会がありますので、気負わずにチャレンジしてみてほしいです。
看板会社は手先が器用でないと入れないと思われがちですが、実際はいろんな人がいて、それぞれ自分ができることが見つけられます。
経験がなくても全く違う分野に触れる機会がありますので、気負わずにチャレンジしてみてほしいです。
長澤:
デザインはお客さんの言葉や想いを形にしていく過程です。
新店舗オープンなど、多くの人の門出に立ち会い、お手伝いできることはやりがいにつながっています。
看板は売上や集客に大きく影響するので、自分が携わったお店が繁盛していくのを見るのは、看板屋冥利に尽きますね。
新店舗オープンなど、多くの人の門出に立ち会い、お手伝いできることはやりがいにつながっています。
看板は売上や集客に大きく影響するので、自分が携わったお店が繁盛していくのを見るのは、看板屋冥利に尽きますね。

水溜:
私自身も看板業界と無縁の業界から来ましたが、建築は技術職なので口だけでは教えにくい限界があります。
当社は創業から24年の実績と業界での顔の広さがあるので、経験できる仕事がたくさん入ってきます。特定の看板に特化していないため、幅広く経験ができる環境です。
特定の技術しかない方でも、知識を身につけながら成長できる会社だと思いますので、自信を持って来てください。
当社は創業から24年の実績と業界での顔の広さがあるので、経験できる仕事がたくさん入ってきます。特定の看板に特化していないため、幅広く経験ができる環境です。
特定の技術しかない方でも、知識を身につけながら成長できる会社だと思いますので、自信を持って来てください。


小嶋:
営業は仕事の入口です。お客さんの意向をしっかり聞いて、それをデザインや製作、現場に正確に伝えることが大切です。
社内に100%伝えきることを目指しています。全ての部署が一つのサインエフェクトの商品として機能するよう、全体を見ています。
最初に話したことと違う結果になっては大問題なので、初めの打ち合わせから最後の完成まで、管理しながら関わるという気持ちでやっています。
社内に100%伝えきることを目指しています。全ての部署が一つのサインエフェクトの商品として機能するよう、全体を見ています。
最初に話したことと違う結果になっては大問題なので、初めの打ち合わせから最後の完成まで、管理しながら関わるという気持ちでやっています。
まとめ – チーム力が生む大きな成果

看板製作は一人ではなし得ない、チームの力が必要な仕事です。サインエフェクトでは各部署の専門性を最大限に活かし、お互いの知識と経験を共有しながら、大型案件にも柔軟に対応しています。
技術的な制約がある中でも創意工夫を凝らし、クライアントの要望に応える高品質な看板を提供し続けることで、信頼を獲得してきました。そして何より、一人ひとりがチームの一員として責任を持ち、成長できる環境があります。
あなたの創造力や技術を街の景観に形として残してみませんか?
未経験からでも挑戦できる環境と、一人ひとりの意見を尊重するチーム体制があります。
看板製作の技術と経験をお持ちの方はもちろん、これから身につけたいという意欲のある方も大歓迎です。私たちと一緒に福岡の街並みを彩りましょう。あなたの手がけた看板が、何年も何十年も街に残り、多くの人の目に触れる—そんな誇りある仕事があなたを待っています。

あなたも私たちの仲間になって、
形に残る仕事を一緒にしませんか?

